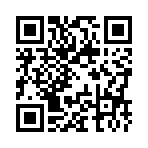2011年11月12日
経験が教えてくれるのは・・・・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
番外編:にやり。なるほど。(54)【経験】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●経験が教えてくれるのは、経験からは何も学べないということだ。
アンドレ・モーロア(作家)
2011年11月12日
3分で人生を変える言葉(科学者編)(61)
●私たちは全て、各自の仕方で真理を探し、各自、なぜ私たちはここにいるのかという問いに答えを望む。
人類が説明の山をよじ登るとき、各自の世代は、前の世代の肩の上に立って勇敢に頂上を目指す。
ブライアン・グリーン (物理学者)
「超ひも理論」研究の先鋒でありながら、「一般人に理論を啓蒙する活動」に努めているのがグリーン博士。
どんなに革新的な考えであっても、結局はその理論を普通の人たちが認識できなければ、世界は動かない。
文明が発展するのは一部の科学者のみの努力ではない。
私たちにもまた、「知ろうとする心」が必要とされているのだ。
人類が説明の山をよじ登るとき、各自の世代は、前の世代の肩の上に立って勇敢に頂上を目指す。
ブライアン・グリーン (物理学者)
「超ひも理論」研究の先鋒でありながら、「一般人に理論を啓蒙する活動」に努めているのがグリーン博士。
どんなに革新的な考えであっても、結局はその理論を普通の人たちが認識できなければ、世界は動かない。
文明が発展するのは一部の科学者のみの努力ではない。
私たちにもまた、「知ろうとする心」が必要とされているのだ。
2011年11月12日
発想力を鍛えるコツ(7)
●没になった企画の見直しをする
会社には、過去に没になった企画がおそらく山のようにあるはずです。
それらがなぜ没になったのか、その理由を考えることも、使える企画を生み出すためには欠かせないステップだと言えます。
本当に内容が悪かったのか、タイミングが早すぎたせいではないのか、という視点で、もう一度、死蔵されている企画のストックをひっくり返してみてください。
なかには、ちょっと磨くだけで玉のように輝き始めるものが現れるかもしれません。
会社には、過去に没になった企画がおそらく山のようにあるはずです。
それらがなぜ没になったのか、その理由を考えることも、使える企画を生み出すためには欠かせないステップだと言えます。
本当に内容が悪かったのか、タイミングが早すぎたせいではないのか、という視点で、もう一度、死蔵されている企画のストックをひっくり返してみてください。
なかには、ちょっと磨くだけで玉のように輝き始めるものが現れるかもしれません。
2011年11月12日
成功する方法(5)●手帳の習慣、メモ、ノートの習慣
ほとんどの人が、年末になると新しい手帳を用意さえると思う。
来年こそ、きちんとした計画を立て、それに従っていくぞ! とか、何かいいことがあるんじゃないかと希望を持ったりする。(それはそれでいいことだ。)
しかし、実際に、意識して手帳を活用できるまではいっていない人が多いのが現実だろう。
僕は手帳に、自分の分身であると思っている。
そこに、自分の信念や信条、人生の目標、短期の目標を書き入れいている。
手帳を見れば、僕が人生で大切にしようと思っているもの、自分の方向性、自分の現在がよくわかる。
一生のスパンを見つつ、5年後、そしてこれからの1年、今月、今週、今日を見る。
手帳には、当たり前だが、予定を書き入れる。
仮に、突然、電話が入ってきて、予定を入れてほしいと依頼が来たりする。(よく来る。)
そのとき、その要件が、自分の人生、自分の今の時点でどんな意味があるのかがひと目で分かる、というわけだ。
まず、自分の価値観、大事にすべきものは何かを確立し、そして、それに基づいて人生目標を立てよう。
それに手帳に書きこんでおく。
上司から「今日、つき合ってくれ」と言われても、彼女との大事なデートがあるならば、「申し訳ありません。今日は大事な予定があります」と断るべきだ。
よい情報、よい言葉、人生上のよいアドバイスがあったときなど、きちんとメモやノートを取っておくべきだ。
このためにも自分の「お気に入りのノートやメモ帳」をいつも持ち歩いていたいものだ。
来年こそ、きちんとした計画を立て、それに従っていくぞ! とか、何かいいことがあるんじゃないかと希望を持ったりする。(それはそれでいいことだ。)
しかし、実際に、意識して手帳を活用できるまではいっていない人が多いのが現実だろう。
僕は手帳に、自分の分身であると思っている。
そこに、自分の信念や信条、人生の目標、短期の目標を書き入れいている。
手帳を見れば、僕が人生で大切にしようと思っているもの、自分の方向性、自分の現在がよくわかる。
一生のスパンを見つつ、5年後、そしてこれからの1年、今月、今週、今日を見る。
手帳には、当たり前だが、予定を書き入れる。
仮に、突然、電話が入ってきて、予定を入れてほしいと依頼が来たりする。(よく来る。)
そのとき、その要件が、自分の人生、自分の今の時点でどんな意味があるのかがひと目で分かる、というわけだ。
まず、自分の価値観、大事にすべきものは何かを確立し、そして、それに基づいて人生目標を立てよう。
それに手帳に書きこんでおく。
上司から「今日、つき合ってくれ」と言われても、彼女との大事なデートがあるならば、「申し訳ありません。今日は大事な予定があります」と断るべきだ。
よい情報、よい言葉、人生上のよいアドバイスがあったときなど、きちんとメモやノートを取っておくべきだ。
このためにも自分の「お気に入りのノートやメモ帳」をいつも持ち歩いていたいものだ。
2011年11月11日
●成功するための習慣の3つの要素
習慣は「知識」と「スキル」と「やる気」という3つの要素からなっている。
知識は「何をするか」または「なぜそれをするか」という2つの質問に答えてくれる。
スキルは「どうやってするか」を示すものだ。
やる気は動機であり、「それを実行したい」という気持ちだ。
生活の中で習慣を確立するためには、この3つの要素がどれも必要である。
成長と変化のプロセスは、上向きのらせん状の循環だ。
つまり、自分のあり方を変えることによって見方が変わり、見方が変わることによってさらにあり方が変わる。
知識・スキル・やる気のレベルが高まるにつれて、古いパラダイムから解き放たれ、生活や人間関係がさらに高い効果性の領域に入ることになる。
そして、このプロセスは常に上向きに続く。
時として、このプロセスを難しく感じることもあるだろう。
生活を変化させるには、大きな目的によって動機づけられる必要がある。
今すぐ欲しい結果を我慢して、将来、本当に得たい結果を追求しなければならないからだ。
しかし、このプロセスこそが、私たちの存在目的である幸福を作り出すものだ。
幸福とは、最終的に欲しい結果を手に入れるために、今すぐ欲しい結果を犠牲にすることによって得る果実にほかならない。
知識は「何をするか」または「なぜそれをするか」という2つの質問に答えてくれる。
スキルは「どうやってするか」を示すものだ。
やる気は動機であり、「それを実行したい」という気持ちだ。
生活の中で習慣を確立するためには、この3つの要素がどれも必要である。
成長と変化のプロセスは、上向きのらせん状の循環だ。
つまり、自分のあり方を変えることによって見方が変わり、見方が変わることによってさらにあり方が変わる。
知識・スキル・やる気のレベルが高まるにつれて、古いパラダイムから解き放たれ、生活や人間関係がさらに高い効果性の領域に入ることになる。
そして、このプロセスは常に上向きに続く。
時として、このプロセスを難しく感じることもあるだろう。
生活を変化させるには、大きな目的によって動機づけられる必要がある。
今すぐ欲しい結果を我慢して、将来、本当に得たい結果を追求しなければならないからだ。
しかし、このプロセスこそが、私たちの存在目的である幸福を作り出すものだ。
幸福とは、最終的に欲しい結果を手に入れるために、今すぐ欲しい結果を犠牲にすることによって得る果実にほかならない。
2011年11月11日
成功への習慣(1)●人格は習慣から成り立っている
私たちの人格は、繰り返される習慣の結果として育成されるものである。
思いの種を蒔き、行動を刈り取り、行動の種を蒔いて習慣を刈り取る。
習慣の種を蒔き、人格を刈り取り、人格の種を蒔いて人生を刈り取る。
つまり、思い⇒行動⇒習慣⇒人格⇒人生 なのだ。
習慣が私たちの生活に決定的な影響を及ぼしている。
習慣によって無意識のうちに生活のパターンが決まっている。
生活のパターンから人格が育成され、そして生活そのものが効果的あるいは非効果的なものになってしまう。
習慣は学ぶことも、変えることも、捨てることもできる。
しかし、それは応急処置だけでできるものではない。
きちんとしたプロセスと強い決意が必要なのだ。
思いの種を蒔き、行動を刈り取り、行動の種を蒔いて習慣を刈り取る。
習慣の種を蒔き、人格を刈り取り、人格の種を蒔いて人生を刈り取る。
つまり、思い⇒行動⇒習慣⇒人格⇒人生 なのだ。
習慣が私たちの生活に決定的な影響を及ぼしている。
習慣によって無意識のうちに生活のパターンが決まっている。
生活のパターンから人格が育成され、そして生活そのものが効果的あるいは非効果的なものになってしまう。
習慣は学ぶことも、変えることも、捨てることもできる。
しかし、それは応急処置だけでできるものではない。
きちんとしたプロセスと強い決意が必要なのだ。
2011年11月10日
一流の仕事術●2)「できる人」とは
一流の仕事術●2)「できる人」とは、できる理由を説明できる人である
できる人は、結果が出たとき、それを客観的に見ることができる。(この点で言うと、長嶋茂雄は「できる人」ではなく、「天才」だった。)
たとえば、あなたがモニターとして実績をあげているのであれば、「なぜ、あなたはそんなに業績がいいのか」と聞かれたら、答えることができるだろうか。
「なぜ、うまくいっているのか」の理由をきちんと説明でき、「これからは、こうしたい」という将来像を持って語れる人、それが「できる人」だ。
うまくいった理由も他人に説明ができ、そのうまくいくサイクルを再び回すことができる。
できる人は、結果が出たとき、それを客観的に見ることができる。(この点で言うと、長嶋茂雄は「できる人」ではなく、「天才」だった。)
たとえば、あなたがモニターとして実績をあげているのであれば、「なぜ、あなたはそんなに業績がいいのか」と聞かれたら、答えることができるだろうか。
「なぜ、うまくいっているのか」の理由をきちんと説明でき、「これからは、こうしたい」という将来像を持って語れる人、それが「できる人」だ。
うまくいった理由も他人に説明ができ、そのうまくいくサイクルを再び回すことができる。
2011年11月09日
「できる人」は、こんな特徴を持っている。
これまで多くの新入社員を教育研修していて思った。
「できる人」は、こんな特徴を持っている。
●1)「できる人」とは、凡人から頭ひとつ抜け出た人である。
周囲を見渡してみましょう。
「あの人はできる人だな」と思う人がいませんか?
そうした人たちは、決して、時代の申し子でも、天才でも、スーパーマンでもない。
「あの人みたいになりたいが、自分も頑張ればなれるかもしれない」「その他大勢の凡人から頭ひとつ抜け出ている」というレベルの人だ。
こういう人を目指していこう。
「カリスマ」でも「時代の申し子」でもない、「天才」でもないけれど、「できる人」だ。
「できる人」は、新卒が50人いれば、その中で「頭ひとつ」抜け出ている存在であり、イメージでも存在感トップ3に入るくらいだ。
そこを目指していこう。
特に新人は。
「できる人」は、こんな特徴を持っている。
●1)「できる人」とは、凡人から頭ひとつ抜け出た人である。
周囲を見渡してみましょう。
「あの人はできる人だな」と思う人がいませんか?
そうした人たちは、決して、時代の申し子でも、天才でも、スーパーマンでもない。
「あの人みたいになりたいが、自分も頑張ればなれるかもしれない」「その他大勢の凡人から頭ひとつ抜け出ている」というレベルの人だ。
こういう人を目指していこう。
「カリスマ」でも「時代の申し子」でもない、「天才」でもないけれど、「できる人」だ。
「できる人」は、新卒が50人いれば、その中で「頭ひとつ」抜け出ている存在であり、イメージでも存在感トップ3に入るくらいだ。
そこを目指していこう。
特に新人は。
2011年11月08日
成功へのビジョン(8)●人生をかけるにふさわしい夢
ベンチャー企業は10社のうち9社が長続きしない。
何十年も創業しようという企業に投資をしてきたベンチャーキャピタリストのアン・ウィンブラッドはこう述べている。
創業者がそのビジネスプランについてもっともらしい説明をしても、その中身が創業者自身の独自性あるいは深い関心のあることと何のつながりも認められないとき、「我々はそうした投資には手を出さない。これから創業という企業が成功するためには、どんな企業でも、文字通り彼らの心、魂、そして頭脳の全てをそのベンチャー事業に注ぎ込む必要がある。」
自分を突き動かしているものを認識するための手順を省くと、そのときは、いつまでも続く成功をおさめるための礎となるはずの何かを自分のものにできない、という大きなリスクを冒していることになる。
ある成功者が言うには「起業家は、事業に対する何らかの感覚を持っていなければならない。音痴の人の場合、それは音楽を認識できないということであり、音楽の世界で育たなければ、音楽を認識できないということになる。」
あまりにもよく目にするのは、自分自身の個人的意義との血の通ったつながりがないまま、壮大な計画を立ち上げる人たちだ。
自分の人生にとって大切な個人的な好奇心や情熱といったものとの繋がりを明確に理解していなければ、ベンチャー事業にとっては、結局、失敗に終わってしまうというリスクが、目に見えて大きくなる。
「意欲を燃やして向かう目標、それは何らかの成果をあげることだ。どんな成果があなたの人生にふさわしいのだろうか」と言う人もいる。
この言葉はおおげさに聞こえるかもしれない。
おそらくそうだろう。
とは言っても、私たちの残された人生の中で、これ以上、どれだけの時間を無駄にしようと考えているのだろうか?
経営している対象が家庭であろうと、企業、あるいは国であっても、成功する人は、自分の生きがいに打ち込むことこそが人生をかけるにふさわしい夢だ、という結論にたどりついているのだ。
何十年も創業しようという企業に投資をしてきたベンチャーキャピタリストのアン・ウィンブラッドはこう述べている。
創業者がそのビジネスプランについてもっともらしい説明をしても、その中身が創業者自身の独自性あるいは深い関心のあることと何のつながりも認められないとき、「我々はそうした投資には手を出さない。これから創業という企業が成功するためには、どんな企業でも、文字通り彼らの心、魂、そして頭脳の全てをそのベンチャー事業に注ぎ込む必要がある。」
自分を突き動かしているものを認識するための手順を省くと、そのときは、いつまでも続く成功をおさめるための礎となるはずの何かを自分のものにできない、という大きなリスクを冒していることになる。
ある成功者が言うには「起業家は、事業に対する何らかの感覚を持っていなければならない。音痴の人の場合、それは音楽を認識できないということであり、音楽の世界で育たなければ、音楽を認識できないということになる。」
あまりにもよく目にするのは、自分自身の個人的意義との血の通ったつながりがないまま、壮大な計画を立ち上げる人たちだ。
自分の人生にとって大切な個人的な好奇心や情熱といったものとの繋がりを明確に理解していなければ、ベンチャー事業にとっては、結局、失敗に終わってしまうというリスクが、目に見えて大きくなる。
「意欲を燃やして向かう目標、それは何らかの成果をあげることだ。どんな成果があなたの人生にふさわしいのだろうか」と言う人もいる。
この言葉はおおげさに聞こえるかもしれない。
おそらくそうだろう。
とは言っても、私たちの残された人生の中で、これ以上、どれだけの時間を無駄にしようと考えているのだろうか?
経営している対象が家庭であろうと、企業、あるいは国であっても、成功する人は、自分の生きがいに打ち込むことこそが人生をかけるにふさわしい夢だ、という結論にたどりついているのだ。